| 所在地 | 南信/岡谷蚕糸博物館:岡谷市郷田1-4-8・岡谷美術考古館:岡谷市中央町1-9-8 |
|---|---|
| アクセス:車 | 中央道岡谷ICから5分・10分 |
| アクセス:公共交通 | 岡谷駅から徒歩20分・徒歩5分 |
| 入館可能時間 | 蚕糸博物館:9~17時・美術考古館:10~18時 |
| 休業日 | 水曜と祝日の翌日・12/29~1/3 |
| 料金 |
蚕糸博物館:¥510(小中学生¥310)・美術考古館:¥370(小中学生¥160) 共通入館券:大人¥660(イルフ童画館などにも入れる3館・5館共通入館券もあります) |
| 電話 | 蚕糸博物館 0266-23-3489・美術考古館 0266-22-5854 |
| web |
料金や営業日時などは最新の情報でない場合があります。公式サイトやお電話等で直接ご確認ください。記載内容が正確でない場合も、施設に責任はなく、当サイトでも責任は負えません。
岡谷蚕糸博物館
とっておき情報
 諏訪式繰糸機(岡谷市提供)
諏訪式繰糸機(岡谷市提供)岡谷蚕糸博物館は、養蚕・製糸・絹に関する展示を行う博物館です。岡谷地方は、上田と共に、信州でも最も製糸業が栄えたところで、蚕糸博物館では、世界遺産の富岡製糸場で使われた最初のフランス式繰糸機(日本で唯一現存)や、国産の諏訪式繰糸機など貴重な機械など3万点もの機械・絹製品・資料が展示されています。絹製品の中には、珍しい、戦時に作られた絹の歯車もあります。
蚕糸博物館は、2012年まで岡谷市役所の近くにありましたが、2014年8月に新築移転し、「シルクファクトおかや」という愛称も付けられました。「ファクト」は、英語のファクトリー(工場)とファクト(事実(を伝える))を兼ねています。
近くにあった製糸工場の「宮坂製糸所」も館内に移転したため、実際に製糸を仕事として行う様子を間近で見ることができる、異色の博物館となりました。春~秋には、養蚕もしていて、糸取りやまゆアート作りの体験もできます。「繭人形セット」などの販売もされています。
宮坂製糸所は、全国で数軒しか残っていない製糸会社の中でも、今も昔からの手作業で、独特の風合いを持つ絹糸を繰っている唯一の工場で、NHKのTVで紹介されたこともあります。
岡谷蚕糸博物館の横にあった美術考古館も、2013年11月に、岡谷駅・イルフ童画館の近くの商店街に移転オープンしました。岡谷市内の美術作品や、遺跡から発掘された土器・石器類を展示しています。重要文化財の縄文時代の顔面の装飾の付いた土器もあります。
養蚕と製糸業は
 桑の葉の上の蚕と繭
桑の葉の上の蚕と繭桑畑で取れる桑の葉で蚕を飼い、その繭から絹(シルク)の生糸を紡ぐのが、養蚕と製糸業です。
明治~昭和初期に日本が外貨を稼いだ主要産業で、特に、信州では多くの農家が蚕を飼い、「お蚕さま」と呼んで大切に育てました。その一方で、映画・小説の「あヽ野麦峠」などで知られる女工哀史の舞台となりました。
その後、1929年の世界大恐慌による繭価の大暴落をきっかけに製糸業は廃れ、桑畑は果樹園などに、製糸業は精密機械工業などに転換しました。
信州では、今もあちこちで、田畑の隅に少し残された桑の木を見かけます。養蚕農家と製糸工場も、わずかですが残っています。
岡谷蚕糸博物館(シルクファクトおかや)・岡谷美術考古館の公式新着情報
2026.2.15 以前勤めていた独立行政法人農業生物資源研究所、現農研機構(つくば市)の後輩ご夫妻が岡谷蚕糸博物館を訪れて頂きました😊
着物大好きな奥様、奥様につられて着物大好きになった旦那さん、帽子がなんとも似合う〜、着こなしが板についてる〜
いつもお二人、手を繋いでいました。羨ましい〜
#農研機構 #岡谷蚕糸博物館
#独立行政法人農業生物資源研究所
2月 15

2026.2.15 今日はオーストラリア🇦🇺から母娘が見えました。2週間の日本旅行で、お母さんがシルク大好きで、糸を求め岡谷蚕糸博物館へ来て頂きました。糸繰りの様子を見て感激していました!
#岡谷蚕糸博物館
2月 15

[新年度(令和8年度)シルク岡谷次世代担い手育成プログラム参加者の募集(受付開始3/1(日)9時〜)]
同プログラムは、岡谷蚕糸博物館(市ブランド推進室)主催による、岡谷シルク推進事業「蚕糸業の歴史文化の伝承」の教育プログラムです。6年目を迎えるこのプログラムでは、年間の実習活動を通じて「養蚕から生糸の製造、製品化に至るプロセス」への理解や興味を深め、将来、シルクの魅力を発信する人材や、研究者、技術者、起業家等としてシルク産業の発展を担う人材の育成を目的としています。
≪定員≫10人 (先着順)
≪対象者≫成人の方(居住地は問いません)
≪条件等≫
・桑園での畑仕事ができる方、カイコの世話ができる方
・年間を通じ、できる限り全日程(20回程度)への参加を考えている方
・実施場所に各自で直接集合いただく場合がありますので、鉄道、タクシー等をご利用の方は、事前にお知らせください。
・当館では当プログラム活動の様子を報道、SNS等で発信していきますので、メディアによる取材、撮影等にご協力をお願いします。
≪受講料等≫参加料年額7,000円、傷害保険料年額820円
≪募集期間≫ 3月1日(日)9時~ 定員になり次第終了
≪申込方法≫電話のみにてお申込み受付
氏名、住所、連絡先等を登録させていただきます。
※お申込み先:岡谷蚕糸博物館 電話 0266-23-3489
スケジュール等詳細は岡谷蚕糸博物館ホームページをご覧ください。
https://silkfact.jp/news/
#岡谷 #おかや #岡谷シルク #岡谷蚕糸博物館 #宮坂製糸所 岡谷絹工房 養蚕 染織 機織り
2月 15
![[新年度(令和8年度)シルク岡谷次世代担い手育成プログラム参加者の募集(受付開始3/1(日)9時〜)]
同プログラムは、岡谷蚕糸博物館(市ブランド推進室)主催による、岡谷シルク推進事業「蚕糸業の歴史文化の伝承」の教育プログラムです。6年目を迎えるこのプログラムでは、年間の実習活動を通じて「養蚕から生糸の製造、製品化に至るプロセス」への理解や興味を深め、将来、シルクの魅力を発信する人材や、研究者、技術者、起業家等としてシルク産業の発展を担う人材の育成を目的としています。≪定員≫10人 (先着順)
≪対象者≫成人の方(居住地は問いません)
≪条件等≫
・桑園での畑仕事ができる方、カイコの世話ができる方
・年間を通じ、できる限り全日程(20回程度)への参加を考えている方
・実施場所に各自で直接集合いただく場合がありますので、鉄道、タクシー等をご利用の方は、事前にお知らせください。
・当館では当プログラム活動の様子を報道、SNS等で発信していきますので、メディアによる取材、撮影等にご協力をお願いします。
≪受講料等≫参加料年額7,000円、傷害保険料年額820円≪募集期間≫ 3月1日(日)9時~ 定員になり次第終了
≪申込方法≫電話のみにてお申込み受付
氏名、住所、連絡先等を登録させていただきます。
※お申込み先:岡谷蚕糸博物館 電話 0266-23-3489スケジュール等詳細は岡谷蚕糸博物館ホームページをご覧ください。
https://silkfact.jp/news/#岡谷 #おかや #岡谷シルク #岡谷蚕糸博物館 #宮坂製糸所 岡谷絹工房 養蚕 染織 機織り](https://shinshu.net/wp-content/plugins/instagram-feed-pro/img/placeholder.png)
2026.1.24
岡谷蚕糸博物館館長さんの講演会に行って来ました。
インドの蚕糸業についてさまざまなお話が聞けて学ぶところが多かったです。
ますますお蚕様に興味津々です。
ショップで糸も買い、何も作るか思案中。
絹糸はもっと身近であるべきだと思います。
光照寺さんでお蚕様の供養塔に手を合わせ、厳かな気持ちになりながら、その後は絹工房さんの帯留創作体験へ。
お蚕様、絹まみれの1日。
今後の何かの糸口を見つけた気がしました。
#岡谷蚕糸博物館
1月 24

2025.11.9(日)
🇫🇷富岡製糸場フランスウィーク2025🇫🇷
富岡製糸場を通して、フランスを体験しよう🎩🥐🍷
富岡製糸場は、明治5年
フランス人技師ポール・ブリュナの指導のもと
明治政府によって建設されました!
フランスと富岡は明治初期からシルクの糸で結ばれてきたのですね🪢
そのブリュナの生誕地『ブール・ド・ペアージュ市』と『富岡市』が
友好都市協定を結んでから10周年となりました✨️✨️
それを記念しての開催となってます💁🏼♀️
開催期間:2025.11.4(火)~2025.11.30(日)
中の人は
富岡製糸場 国宝・西置繭所で開催されている
「日仏交流が織りなすシルクの魔法」展を体感してきました。:°ஐ..♡*
ブール・ド・ペアージュ市の主要産業であった「フェルト帽」や
富岡製糸場の関連施設である「セルドン銅工場」や「ボネ絹工場」の紹介
そして今回の見どころは
富岡市初公開《ブリュナの応接セット(岡谷蚕糸博物館所蔵)》!!
絹張りのソファとカウチは当時の暮らしぶりが伝わりますね🛋
ほかには
フランス生まれの高品質な繭「セヴェンヌ」を
富岡の養蚕農家さんが育て
その繭から生まれた「富岡シルク」が
様々なファッションアイテムとなっていく未来を
細尾真生氏(映画「マダム・ソワ・セヴェンヌ」プロデューサー)デザイン展示
館内特設カフェスペースも期間限定のオープンです𓂃𖠚ᐝ
☕️富岡フレンチブレンドコーヒー☕️をぜひ〜
#富岡製糸場
#国宝西置繭所
#世界遺産富岡製糸場
#富岡製糸場フランスウィーク
#富岡製糸場フランスウィーク2025
#フランス
#ブールドペアージュ市
#富岡市
#ポールブリュナ
#ポールブリュナの生誕地
#日仏交流
#日仏交流が織りなすシルクの魔法
#フランスを体験しよう
#セルドン銅工場
#ボネ絹工場
#ブリュナの応接セット
#岡谷蚕糸博物館
#細尾真生 さん
#セヴェンヌ
#大和屋
#富岡フレンチブレンド
#期間限定カフェ
#セカイト
#群馬県立世界遺産センター
#世界遺産ガイダンス施設
#ぐんまきぬ旅
#きぬ旅
#フォローお願いします
my.tomioka
silkfactokaya
yamatoya.takasaki
11月 9

『日本絹文化フォーラム2025(7th)』開催
絹文化に関する講演や情報交換を行う
「日本絹文化フォーラム」が開催されます‼︎
着物や絹を纏いご参加いかがですか?🥰
申し込み先
silkfactokaya
日本絹文化フォーラム実行委員会事務局
岡谷蚕糸博物館
TEL 0266-23-3488
FAX 0266-22-3675
#絹
#国産絹
#シルク
#岡谷蚕糸博物館
#日本シルクワーカーズ
#養蚕
#蚕
#シルクワーカーズ
9月 17

大人の修学旅行!
昨日は長野県は岡谷市の岡谷蚕糸博物館へ見学に伺いました。
岡谷市は養蚕・製糸業の一大産地だったのですね。
展示を通して、良い絹糸をよりたくさん作るために、様々な試行錯誤の歴史があったことを知りました。
上田紬の染織家・小山憲市さんの特別展が開催中ということで、そちらも拝見しました。
弊店も長年お世話になっている小山憲市さんの、これまでの軌跡を見ることができる、大変見応えのある作品展でした。
11月は弊店にて小山憲市さんの作品展を予定しています!
今からとても楽しみです✨
________________
神戸・元町 丸太や
神戸市中央区元町通1-7-2
Tel 078-331-1031
営業時間 10:30〜19:00
定休日 水曜日
________________
#岡谷蚕糸博物館
#着物
#上田紬
#小山憲市
#神戸着物
#呉服屋
8月 27

お盆休み満喫です
#おかだの休日 #田舎暮らし #こどのいる暮らし #生活とフィルム #デジタルでフィルムを再現したい #ファインダー越しの私の世界 #写真好きな人と繋がりたい #東京カメラ部 #jp_portrait #photography #reco_ig #team_jp_ #Canon #立石公園 #太養パン #岡谷蚕糸博物館 #観光荘
8月 17

口コミや質問をどうぞ
Facebookのアカウントが必要です
近隣のおすすめ
スポット
蚕や絹の博物館は長野県のここにもあります
近くの宿
by じゃらん Web サービス
近くのお食事処
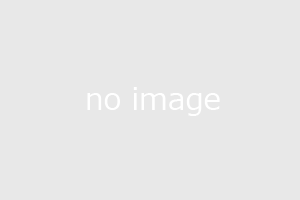
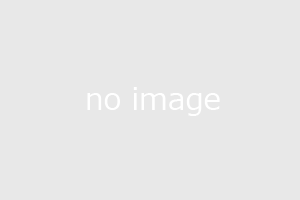




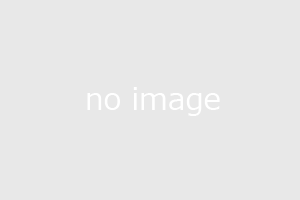





















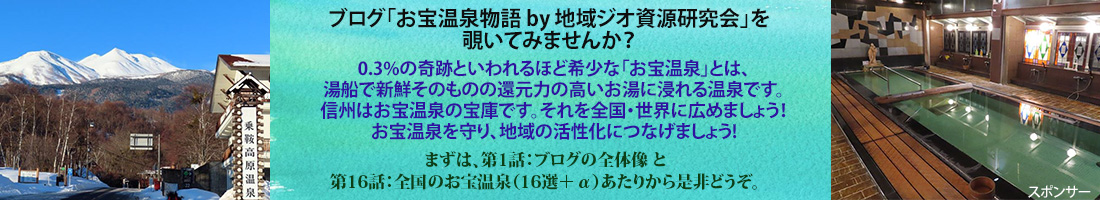




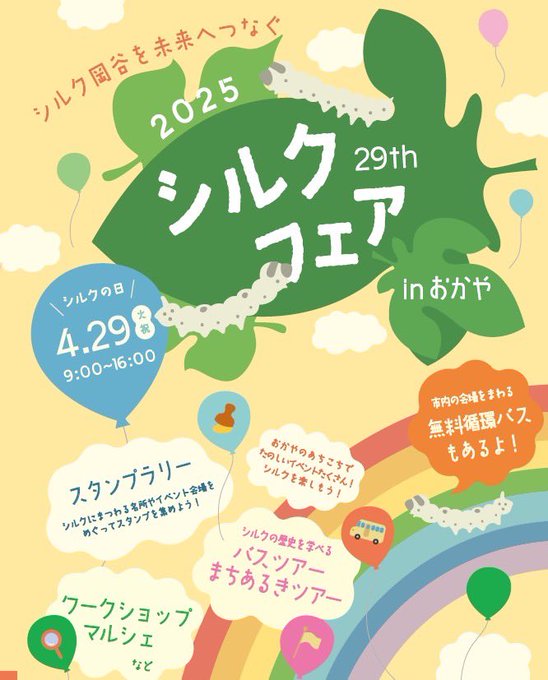






 0266-24-5821
0266-24-5821